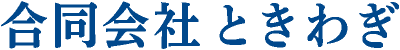News
お知らせ

2025.09.15
るりでのリハビリの特徴
訪問リハビリと当施設でのリハビリを比べられることが多いので、その違いを説明したいと思います。
障害者のリハビリは、高齢者の介護予防的なリハビリとは根本的に目的もアプローチも異なります。しかし、訪問リハビリにおいては、高齢者のリハビリが圧倒的に多いです。ゆえに、障害者のリハビリでは生活環境の観察と個別性の高い支援が不可欠ですが、現行制度ではその実現に限界があるのが現状です。
私自身も訪問リハビリをしていて、訪問リハに限界を感じた一人です。高齢者リハと違い、障害者の場合はお互いに満足のいくリハビリを提供しようと思うと、1件に2時間近く時間がかかりました。しかし、それだけ時間をかけても、週1回の頻度では現状維持すら困難でした。この原因はどこにあるのか?課題は色々考えられますが、最大の原因は、大幅に訪問時間を延長しただけでは、日頃の姿勢や生活環境まで把握し、個々の課題に適したリハビリを行えないということでした。その経験から、じっくりリハビリが提供できる環境があればと強く思うようになりました。るりの施設では日中活動から、短期入所では夜の様子など一日を通して動作や姿勢を観察できるので、個人に合ったリハビリを提供することができます。また、多職種(理学療法士・看護師・介護福祉士・保育士・栄養士・教員など)で支援しているので、観察する視点が違います。それぞれの視点から得た情報を共有できるので、様々なアプローチから個々に合ったリハビリが提供できるところが強みです。
高齢者では2024年以降、「みなし訪問リハ」など新制度の導入が進み、介護施設からの訪問リハ提供が可能になるなど、少しずつ柔軟性が出てきています。高齢者に比べると、障害者福祉制度の改革はまだまだこれからですが、いつか障害者施設からも訪問リハが提供できるようになればいいですね!
🧠 障害者リハビリの特徴と課題
✅ 障害者リハビリの目的
- 機能回復よりも生活の再構築が中心
- 社会参加、就労支援、自己決定の尊重など、より広範な支援が必要
- 年齢や疾患に関係なく、長期的・継続的な支援が求められる
⚠️ 訪問リハビリの制度的限界
- 介護保険では週2回・1回20〜60分程度が上限
- 医療保険での訪問リハは対象者が限定され、利用しづらい
- 生活全体の観察や環境調整には時間が足りない
- 障害者支援の専門性を持つ療法士が少ない地域もある
📚 実際の研究や報告から見える課題
- 訪問リハの利用者は高齢者が中心で、障害者の利用は少数派
- 障害者のニーズに合った支援体制が整っていないため、制度の狭間に落ちてしまうケースも多い
- 「訪問リハビリステーション制度」のような地域密着型の仕組みは構想されながらも、制度化されずに終わったという背景もあります
💡 可能性と提案
- 2024年以降、「みなし訪問リハ」など新制度の導入が進み、介護施設からの訪問リハ提供が可能になるなど、少しずつ柔軟性が出てきています
- 地域包括ケアの中に、障害者の生活支援を組み込む仕組みづくりが求められています